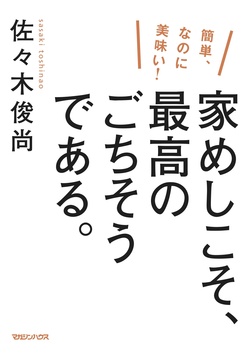【連載】『家めしこそ、最高のごちそうである。』
第2回:1970年代の家庭料理とは?
稀代のジャーナリストが語る、家庭料理の極意。「家めし」の美味しさを追求していったら、答えはシンプルなものへと辿り着いた。第2回は、1970年代の家庭料理を振り返ります。
わたしは1961年生まれで、52歳になります。キリの良い年に生まれたため、70年代が思春期、80年代が20代、バブルのころは20代後半で新聞記者でした。そして「失われた二十年」を30代後半から40代のあいだにすごしてきたということになります。
高度経済成長の末期、1970年代の家庭料理とはどのようなものだったでしょうか。
記憶はたいていの場合、美化されてしまうので、鮮明に覚えている人は少ないかもしれません。でもひとつだけ断言できるのは、そのころの家庭料理っていまとはまったく違うものだったということです。
たとえば作家向田邦子さんが当時つくっていた料理を再現した『向田邦子の手料理』(講談社、1989年)という本があります。向田さんは1981年に飛行機事故で惜しくも亡くなられてしまったのですが、不世出の脚本家でありエッセイストであり小説家でした。『寺内貫太郎一家』や『阿修羅のごとく』『あ・うん』などのホームドラマが有名です。
昭和ひとけた生まれだった彼女が活躍していたのが、1970年代でした。この『手料理』は、そのころに彼女がつくっていた料理を妹さんが再現して本にしたものなんです。
この本のレシピ、いまつくってみてもとても美味しいのでお勧めです。ところが驚かされるのが、食材や調味料の種類が少ないこと。最近はスーパーマーケットに行くと、各種のハーブやアボカド、ロメインレタス、チコリ、ラディッシュ、セロリアックといった西洋野菜が普通に売っています。聖護院ダイコンや賀茂ナスなどの京野菜も普通に東京で手に入るようになりました。
でも向田さんの料理本にはそういう野菜はめったに出てきません。ナスやキュウリ、ピーマン、キャベツ、トマトなどが中心。あとはチコリやブロッコリー、アボカドなどが顔を出す程度でしょうか。こういう野菜は当時としてはかなり珍しい部類だったんじゃないかと思います。
調味料も同じで、醤油と味噌、サラダ油、それにウスターソースとケチャップとマヨネーズぐらいでしょうか。ナンプラーやバルサミコ酢、エクストラバージンオリーブオイル、豆板醤、アンチョビなどといった調味料は影もかたちもありません。
でもそういうありきたりの食材と調味料で、70年代のあのころはヨーロッパ風やエスニック風の料理を工夫してつくっていたということなんです。
たとえば「なすのいため物ロシア風」という向田さんの料理。これはナスとタマネギをみじん切りにして炒め、トマトケチャップとスープストックを加えて塩とコショウで味つけ。レタスやサラダ菜で包んで食べるというものです。妹さんは本の説明で「パンにのせてもおいしい。何ゆえロシアだかは、いまだ不明」なんて書かれています。
「サーモンと玉ねぎのグレープフルーツあえ」というのもあります。タマネギの薄切りを塩でもんで水気を絞り、袋から出したグレープフルーツ、スモークサーモンと一緒にあえて混ぜるだけというシンプルな料理なんですが、これ今つくってみてもとても美味しいです。珍しい食材を使っているわけじゃないのに、ちゃんと地中海風の味になっているのがすばらしいですね。

サーモンと玉ねぎのグレープフルーツあえ
とはいえ、向田さんの料理は、昭和時代の高級な山の手の料理です。向田さんのお父さんは、大手生命保険会社の支店長で、どちらかというと中流の上くらいの家庭だったんですね。もっと下の階層だと、家庭料理はこの時代でもだんだん崩壊しかかっていました。
わたしの母の実家は兵庫県西脇市というのんびりした田舎町で、小さな化粧品店をいとなんでいました。夏休みに帰省するとおばあちゃんがかなり凝った手料理をつくってくれました。電子レンジもない時代に育った大正生まれの人なので、たとえば冷えたご飯や結婚式の引き出物でもらった尾頭付きの鯛の焼き物なんかは、ていねいに蒸し器で温めたりしてたんですね。お盆や正月になると親戚一同が集まってきて、お店兼住宅の二階のふすまをとっぱらって大広間にし、昼間から宴会です。煙草と仁丹のにおいのするおじちゃんたちに子供のころ無理矢理飲まされた(いまだと犯罪扱いされそうですが)、キリンビールの苦い味をふと思いだします。
お盆になるとおばあちゃんは必ず大量のおはぎをつくってくれました。甘味のほとんどない餡に、アズキの香りは濃く、ほとんど潰れていないもち米はお握りのような食感で、大人たちにも人気でした。甘党の人からは「砂糖が足らないよなあ、おばあちゃんのおはぎは」と不評だったようですが。
でも当時のわたしはすっかり化学調味料の味に慣れた生活をしていたので、おばあちゃんの自然な味つけは「なんだか薄いなあ」と好きではありませんでした。高校生のころは帰省してもおばあちゃんの料理にはあまり箸をつけず、あとからこっそり近所のショッピングモールに行ってパック詰めのサンドイッチを買い食いしたりしていました。いま考えるともったいないことをしたなあ、と心底思います。わたしが本格的に料理するようになったころにはおばあちゃんはもう認知症になってしまっていて、料理も忘れてしまっていました。「おばあちゃんが元気なうちに料理を学んでおけば良かった……」と何度思ったことか。
それにしても、料理好きっていう志向は、隔世遺伝するのでしょうか。孫である私はたいへんな料理好きになってしまったのですが、私の母も含めて、おばあちゃんは五人の娘を育てましたが、残念なことに全員があまり料理好きじゃなかったんです。
1970年代、わたしが高校生のころに母親がつくっていた家庭料理というと……「挽肉を炒め、缶詰のミートソースを加えて煮込んだスパゲッティ」「冷凍ミックスベジタブルと炒めたチャーハン」といった、缶詰や冷凍食品の半調理品を使ったものが多かったんです。
そういう料理を食べて、私は育ちました。もともと生まれたのは兵庫県ですが、その後大阪へと流れ、小学校高学年のころにはトヨタ自動車の工員になった父親に連れられて愛知県豊田市に移り、地元の高校を卒業し、上京して早稲田大学に入学しました。大学に入って自炊するようになったのですが、しばらくして帰省した際、母とこんな会話をしたのを覚えています。ひさしぶりに母がご飯をつくってくれ、味噌汁を飲んだときのことです。
ああ、やっぱり美味しいなあ。東京のアパートで自分でつくるのと違うよ。この味噌汁はさあ、佐々木家の味だよねえ
すると母は、急に笑い出してこう言ったのです。「俊尚、それ家庭の味じゃなくて『ほんだし』よ」 わたしが「おふくろの味」だと信じていた味噌汁は、実は母が味の素のうま味調味料『ほんだし』で作っていた味だったというオチなのでした。「そうだったのか……」とがっくり肩を落とすわたし。
思いだせばこのころ、多くの家の食卓には醤油差しと並んで、味の素やアジシオの小びんが置いてあったのを思いだします。漬け物には味の素を振りかけて食べるなんていうのが、わりに一般的だったんです。

佐々木俊尚 作家・ジャーナリスト。 1961年兵庫県生まれ。早稲田大政経学部政治学科中退。毎日新聞社などを経て、フリージャーナリストとしてIT、メディア分野を中心に執筆している。忙しい日々の活動のかたわら、自宅の食事はすべて自分でつくっている。妻はイラストレーター松尾たいこ。「レイヤー化する世界」(NHK出版新書)、「『当事者』の時代」(光文社新書)、「キュレーションの時代」(ちくま新書)など著書多数。
『家めしこそ、最高のごちそうである。』HONZにて集中連載!
第1回 はじめに
第2回 1970年代の家庭料理とは?
第3回 1970年代の外食は、化学物質とまがい物の時代だった!
第4回 外食ブームの陰で家庭料理は
第5回 健康的な食生活はだれでも送れる
第6回 美食でもなく、ファスト食でもなく
第7回 まず最初に、食材から考えること
第8回 「足す」料理と「引く」料理
第9回 【レシピ①】鶏もも肉と白菜だけでつくる究極の水炊き、自家製ポン酢とともに
第10回 【レシピ②】スーパーで売っている「焼きそばセット」を美味しく食べるすごい秘訣
第11回 【レシピ③】見た目も超旨そうになる、絶品キノコ鍋
第12回 【レシピ④】みんなの集まる家呑みで、全員が満足する料理。豪華なちらし寿司。