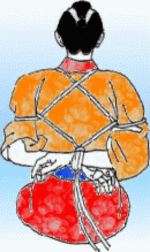趣味性が高く、マニアックな世界の話を外向けにコミュニケーションしているケースというのは、そうそうお目にかかれない。その手の会話の醍醐味はハイコンテキストなやりとりが交わされるという点にあり、前提となる知識が省かれることによって拍車もかかる。ましてや秘匿性の高い話題となれば、なおさらのことだ。しかし水面下では、地下水脈のように文化的な基盤が共有されており、その暗黙知に素人はつまずきやすい。
そういった意味で、本書がアメリカ人の手によって書かれたのは、象徴的なこととも言えるだろう。SMにおけるプレイの一形態に過ぎないこの緊縛という行為は、今や西洋でもそのまま通じる言葉となっており、格闘技や茶道、生花などと同じくらい日本発の文化として世界を席巻し始めているのだという。
だが西洋では、緊縛もその映像も、社会的・歴史的な背景から全く切り離されたものとして見られており、その悲嘆が本書の執筆のきっかけになった。著者は日本への留学経験を持ち、40年以上にわたって緊縛を研究し続けている人物。かつて自身もつまずいたであろう際どい領域の暗黙知を、言わば逆輸入という形で見事なまでに言語化している。
本書における緊縛の定義とは、「安全で官能的でドラマティックでエロティックな拘束のテクニックであり、日本で芸術の域にまで高められたもののこと」を指す。緊縛という技芸にフォーカスを絞ったがゆえに、その起源を日本人の否定しがたい領域に見出すことが出来る。それが日本の最古の宗教とも言われる神道だ。この宗教においては、古より複雑な結びの技巧が用いられてきたのである。
古くは縄紋土器に始まり、注連縄、茅の輪から相撲の回しまで。また、神道と影響し合った仏教においても、不動明王、縛られ地藏などは縄との縁が深いし、文化面においても雪吊り、水引細工などの例がある。さらにインドから伝えられ日本で改良された「四十八手」のうち、「理非知らず」「首引き恋慕」「流鏑馬」「達磨返し」の四体位は、その実行のために縄を用いるよう明記されているというから驚くよりほかはない。
結びは日本文化と切っても切れない実用的かつ神聖な要素である、と著者は言う。なぜなら結ぶこと、縄を用いることは、日本文化の基本的な、宗教的ですらある営みにとって、何世紀ものあいだ不可欠の要素であったからである。緊縛は、単なる拘束の1テクニックと言うよりも、歴史、宗教、文化の奥深い部分とさまざまな点で共鳴している美意識の一側面なのだ。これは西洋におけるSMの起源がキリスト教にあったと言われることとも照らしあわせて考えると、非常に興味深い事実である。
かくも日本人は、性的な縛りと精神世界、宗教を絡み合わせ、調和させてきた。その中でも、現代の緊縛の先駆けとなったものは二つある。その一つが「捕縄術」。緊縛の起源を理解するには多くの鍵があるが、日本が江戸時代の数世紀にわたって諸外国から孤立していたこと、しばしば暴力的な封建体制を過去に経験していることが核心である。この時期に、捕縄術は法執行のための第一の技術となっただけでなく、その洗練と象徴性の度も急速に深めていったのである。
江戸時代の捕縄術の定法の一つに「見た目に美しいこと」という項目があるのは注目に値する。近代以降の緊縛にとってとりわけ重要なのは、効果的な拘束のための実用性と、視覚のための独特な美意識を兼ね備えているという点にあるのだ。この捕縄術における縛りの型に対する美意識は、近代以降のエロティックな緊縛にも大きな影響を及ぼした。
そしてもう一つの先駆けが「罰」というものである。平均的な江戸市民は、日常生活のなかで公的な刑罰を目にすることを免れ得なかった。そして数々の縛りの差異化の結果、驚くべきことに通りすがりの見物人は、どんな縛り方が用いられているか見るだけで、囚人の階級も罪状も、そしておそらくは受ける刑罰も言い当てることができるほどであったという。
縛られること、無法者、除け者となることで覚える恥辱に、日本人は何世紀ものあいだ恐れを抱く一方で魅了されてきた。つまり西洋文化の基本は罪にあるのに対し、日本文化の基本は恥にあるのだ。両者の主な違いは、罪は個人の内面的な心の動きであるのに対して、恥は外的な集団の存在に依拠しているということ。これこそが日本人のSMプレイの重要な心理的側面なのである。
だがこの時代の緊縛というのは、あくまでも公のもので、規範に則ったものに過ぎない。これが私的な「想像力の領域」へと移るまでには、歌舞伎と春画という二つの文化が大きな役割を果たすことになる。暴力的かつ残虐性を持つ場面が進化して作られた「残酷の美」という歌舞伎のコンセプトは有名であるし、責め場という場面は、歌舞伎の演劇技法として繰り返し用いられた。また、春画においても責め絵というジャンルが確立され、江戸時代の縛りと懲罰のイメージをエロティックな空想へと転じるのに一役買ったのである。

恥と罰という刺激的な観念が、広く関心を集めていた歌舞伎と春画に結びつき、緊縛は再現性という武器を手にした。野蛮な歴史が、エロティックな芸術とパフォーマンスへと変貌した瞬間である。
その後も、雑誌、映画、ビデオとステージを移しながら、緊縛は進化を遂げていく。メディアの発達とともにインタラクティブ性を帯び、やがては緊縛のデモクラシーの時代を迎えることになったのだ。だが玉石混交とも言える現在の緊縛シーンに対する、著者の評価は手厳しい。
”素人臭い写真の数々が多様な性的関心のすべてを気前よく満足させてくれてはいるが、どれもが「衝撃度」のみを競い会っているように見える。”
”ポルノがどんどん露骨になり、時に悪趣味で暴力的で間違いなく女性蔑視的なほどにまでなるにつれて、緊縛はこの種の題材に当たり前のように出てくる常套手段となり、代わりに技芸が奪われてしまった。”
”素人にすぐやれそうで、やれば面白そうに描くのがフィクションの世界だから、くれぐれも無責任な虚構の世界のことにだまされないことだ。”
要は「相対尽くの愛し合う関係」という制約上の縛りが消え、何でもありになっている昨今の風潮に一石を投じているのだ。現代の緊縛には、いくつもの異なる歴史的かつ、アーティスティックなルーツがある。単に表層的なインパクトを追うのではなく、狭くも深い歴史を知ることこそが肝要というメッセージは、あらゆる分野に通じる話であるだろう。
本書ではこの他にも、「フォトギャラリー」、「緊縛の歴史における26人の重要人物」、「用語集」、「ハウツー緊縛」などの章によって、緊縛の世界が多面的に紹介されている。偉大なる緊縛師達の精神の発露をつなぎ合わせることで、プロフェッショナル論へと昇華させているのが印象的だ。
緊縛の縄を紐解くことによって見えてくるのは、日本人が「自由」というものとどのように向きあってきたかということの証左でもある。時代と呼応するように希求、戸惑い、拒絶と変遷していく様は、まさに愛憎半ば。「自由」と「拘束」の駆け引きが紡いできた物語を、ぜひ色眼鏡を外してご覧いただきたい。