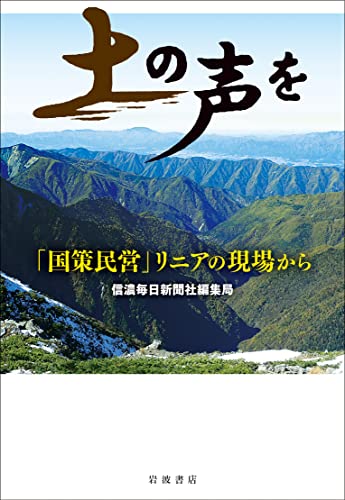長野県は「北高南低」である。
県北部に位置する長野市は、1998年長野冬季五輪の開催都市となり、前年97年に長野新幹線(現北陸新幹線)東京−長野間が開通した。これにより所要時間は従来の半分の1時間半ほどに短縮された。
かたや県南部の飯田市はどうか。鉄道はJR飯田線があるものの、天竜川沿いを縫うように走るため時間がかかる。東京・新宿に行くのに最速は中央道を走る高速バスだが、所要時間は実に4時間超え。長野市に行くのでさえ3時間かかるという。まさに「陸の孤島」である。
そこに降って湧いたのが「リニア中央新幹線」の話だった。
リニア中央新幹線は73年に基本計画路線となり、78年に旧国鉄が長野県内の路線について、A(諏訪・木曽谷回り)、B(諏訪・伊那谷回り)、C(南アルプス貫通)の3ルートを提示した。長野県は89年、Bルートの実現を目指す方針で一本化したが、2007年に局面が変わる。JR東海が自己資金で開業を目指す方針を示し、東京・品川−名古屋間を最短で結ぶため、南アルプスを貫くCルートを選んだのだ。
Cルートだと飯田市に駅ができる。開通すれば東京まで45分、名古屋まで25分という夢のような時間短縮が実現することになる。
だが、これははたして地元にとって良いことだったのか。
本書は、信濃毎日新聞の世評高き連載企画を書籍化したものだ。リニア建設の現場を記者が丹念に歩き、事実をひとつひとつ積み上げた連載は高く評価され、日本ジャーナリスト会議JCJ賞、新聞労連ジャーナリズム大賞を受賞した。
リニアといえば、知られているのは「水」の問題かもしれない。南アルプスのトンネル掘削に伴う大井川の流量減少を懸念して、静岡県の川勝平太知事は現在も静岡工区の着工を認めていないが、リニア建設をめぐる問題はこれだけではなかった。実は信州で表面化しているのが「土」の問題なのだ。
品川−名古屋間の86%はトンネル区間である。それだけ穴を掘れば大量の土が出るのは理の当然で、JR東海は掘削工事で出る残土の量を5680万立方メートル(東京ドーム46個分)と見込む。長野県に限れば、974万立方メートル(同8個分)。この残土をどうするかが、待ったなしの問題になっている。
飯田高校の校歌には「ああ白雲の谷深く 都の塵も通ひこぬ」という一節があるという。都会から遠く離れた山々が連なる土地のイメージが浮かんでくるが、残土置き場の候補地に選ばれたのは、まさに校歌に謳われるような山に挟まれた深い谷や沢だった。人里離れた沢や谷筋を埋め立てるのは一見、悪くないアイデアに思えるかもしれない。だが、地元には恐ろしい災害の記憶が残る。
南木曽町の74歳の男性は、1965年7月1日の体験がいまも忘れられないという。高校で試験を受けていた午後3時頃、ゴォォォと異様な地響きがした。「おいっ、抜けてくるぞ」と同級生が叫んだ。木曽川を挟んで対岸の支流に目を向けると、木々が立ったままゆっくり沢を落ちてくるのが見えた。続いて激流とともに大きな石が次々に転がってきた。土石流だ。巨大な蛇が沢筋を這うように見えることから、地元では土石流を「蛇(じゃ)抜け」と呼ぶ。町には土石流災害が繰り返されてきた歴史がある。
伊那谷でも人々の記憶に残る災害があった。61年の豪雨災害「三六(さぶろく)災害」である。天竜川の上流で大規模な氾濫が発生し、各地で土砂崩れや土石流が起きた。死者・行方不明者は136人、浸水戸数は1万8488戸に上った。
こうした災害の記憶に加え、2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害が住民たちを不安にさせている。流れ出た大量の土砂には建設残土が含まれていたからだ。
JR東海が候補とする残土置き場の中には、土石流の危険がある場所も含まれていることが取材で明らかになった。ところが、こうした危険性は、住民たちに説明されていなかった。なぜ十分な情報公開がなされていないのか。それは、リニアが民間の事業だからである。JR東海は自己資金でリニアを建設する。民間の事業だから国や自治体のように情報公開の対象ではないという理屈だ。ここにリニア計画がはらむ構造的な問題がある。
リニア建設は国の事業なのか、それとも民間の事業なのか。本書のサブタイトルにある「国策民営」という言葉は、見事にこの問題の本質をとらえている。
そもそもリニア中央新幹線構想は、田中角栄にはじまる。1972年に著書『日本列島改造論』の中で、全国を新幹線網で結ぶ構想をぶちあげ、「第二東海道新幹線」は「リニアモーター形式で」と書いた。この実現に執念を燃やしたのがJR東海名誉会長の葛西敬之であり、後押ししたのが当時の安倍晋三首相だった。
森功氏の『国商』に詳しいが、「国策」を錦の御旗に掲げるリニア計画の裏には、葛西と安倍の個人的な関係があった。安倍政権の下、2016年に国の資金を民間銀行よりも大幅に低い金利で貸す財政投融資を活用し、JR東海に計3兆円を融資することが決まったのは、両者の親しい関係があったからだろう。
葛西と安倍が亡くなった後も、リニア建設は「国策民営」という奇妙な性格を帯びたまま続けられている。さらに本書を読みながら感じたのは、JR東海も国も、「国策」と「民営」をその時々で都合よく使い分けているのではないかということだ。
例えば、リニア本線や新駅の工事に伴い、住民に立ち退きの交渉を行なっているのは、地方自治体の職員である。用地交渉を県や市がJR東海の代わりに担うのは、「全国新幹線鉄道整備法」という法律に根拠があるからだが、飯田市のリニア用地課の職員の中には、住民との板挟みになり「夜眠れない」「朝、仕事に行くのが嫌だ」という職員もいるという。まるでJR東海の下請け業者の悲哀を聞かされているようだ。
一方、情報公開に関しては、JR東海は民間であることを盾に不誠実な対応に終始している印象を受ける。本書はリニアの電力消費の問題にも光を当てているが、JR東海は自社の東海道新幹線との消費電力の比較データを頑なに明かさない(公式にはデータが「ない」との説明)。リニアは時速500キロのスピードと引き換えに新幹線に比べ多くの電力が必要になるはずだ。しかもJR東日本が消費電力の約6割を自前の水力発電や火力発電で賄っているのに対し、JR東海には自前の発電所がないという。いざという時の備えは大丈夫だろうか。
本書で初めて知ったことは多い。トンネル掘削では深夜でも発破が使われ、住民たちの安眠を妨げていること。残土を運び出すトラックが細い道をひっきりなしに走り、沿線の温泉地はせめて週末だけでも運休してほしいと悲鳴をあげているがほとんど聞き入れられないこと。リニアに電力を供給する送電線の鉄塔工事ではヘリコプターによる山中の資材運搬が行われ、住民は騒音被害を訴えるが、騒音規制法はヘリには適用されないこと……。巨大事業をめぐり、今も現場ではさまざまな問題が起きている。
国鉄がリニアモーターカーの研究を始めたのは1962年だという。研究が始まって60年。本書は、「夢の超特急」計画はいつの間にか、時代の速さに追い越されていないかと疑問を投げかける。
長野県は2013年にまとめた試算で、リニア県内駅の乗降客数を1日約6800人と推計。リニアを利用して県外と行き来する場合の「時間短縮便益」(既存の交通手段に比べ短縮した移動時間を貨幣価値に換算)は年間約110億円とした。
このような数字にはもはや意味はない。本書に登場する菓子製造販売会社の担当者は、コロナ前は商談や催事で国内外を飛び回り、飯田市の自宅に帰るのは「月に数日」だったが、オンラインが当たり前となった今は泊りがけの県外出張は月に1、2回だという。時代はとっくにリニアよりも先に進んでいるのだ。
本書のタイトル「土の声」には取材班のこだわりが込められている。「土」は、大都市圏の利便性を高めるために翻弄される地方のこと、巨大事業に押しつぶされそうな地域の名もなき小さな声を意味しているという。
人は大地の上に生きている。ならば私たちにもその小さな声は聴き取れるはずだ。「土の声」に耳を傾けようとしない者は、やがて大きなツケを払うことになるかもしれない。