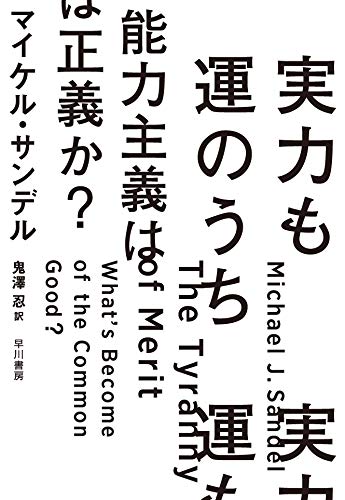「運も実力のうち」という慣用句はよく聞くが、「実力も運のうち」というのはどうだろう。「実力」という言葉はフェアに聞こえるが、それが単に「生まれ」という「運」による幻想にすぎないとしたら。
そうした不都合な真実に切り込んだのが、米ハーバード大学のマイケル・サンデル教授による本書である。原題は“The Tyranny of Merit”、直訳すれば「能力の専制」だが、巻末の解説によれば“merit”の原義は日本語の「能力」よりも「功績」に近いという。
つまり、この原題が表しているのは「功績、とくに学歴という結果によって人生が決まってしまう能力主義(メリトクラシー)という仕組みの横暴」となる。
「学歴」は、ある人がその大学に入学できたという能力の証であり、功績でもある。しかし、現実を見れば、ハーバード大学の学生の3分の2は所得で上位5分の1に当たる家庭の出身だという。にもかかわらず、彼らは自分が入学できたのは努力と勤勉さのおかげだと思っている。
米国人は、米国が人種、性別、出自によらず努力すれば成功を手にできる機会を平等に与えられた社会だというアメリカンドリームを信じてきた。しかし今、こうした能力主義がエリートを傲慢にし、勝者と敗者との間に未曾有の分断をもたらしている。
そして、これは米国だけの現象ではなく、ヨーロッパで行われた社会心理学者のチームによる調査でも同様だった。大学教育を受けた回答者たちは、教育水準の低い人たちへの偏見が、そのほかの不利な立場にある集団(職業、人種、性別など)への偏見よりも大きかった。つまり、今日のように人種差別や性差別が糾弾される時代にあって、学歴偏重主義は広く容認されている最後の偏見なのである。
その理由は、能力主義に基づく自己責任という考え方にある。貧富や所属階級の差と違って、学業成績が悪いのは個人の努力不足のためであり、大学へ行けなかったのは本人の落ち度だと思われている。しかも、学歴の低い人々自身でさえこうした見方を共有しており、自らが置かれている現状を招いた責任は自分にあると考えている。
これほどまでに、能力主義の呪縛は社会全体に深く浸透し、多くの人々の自信を失わせているのである。したがって、能力主義社会では、教育こそが社会問題を解決すると強調すればするほど、地位の低い集団がさらに低く評価されることを招いてしまう。
能力主義の社会では、人種、階級、性別などに関係なく、誰もが平等に成功につながる学歴を手にすることができるはずだった。それが本当の意味での平等であり、であれば成功した人はそれに相応しい報酬を手にするべきだとされた。それが、本来の能力主義の約束だった。
しかし実際には、能力主義とグローバリゼーションは巨大な不平等をもたらした。1980年代以降の米国では、上位10%の富裕層が利益の大半を懐に入れ、下位50%の人々は何も得ることができなかった。
新たに出現したこの階級社会を正義にかなう共同体へと変えることはできるのか。それが、サンデル教授が投げかける大きな問いなのである。
※週刊東洋経済 2021年6月19日号